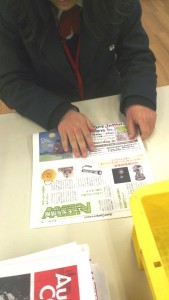2015.12.15
青葉通信2月号巻頭言
事業所長 武者明彦

通勤途中にとおる住宅地は、季節ごとに各家の植込みの花が変わります。先日までは真っ赤なサルビアが植わっていたのに、気が付いてみたら、いつのまにかパンジーに代わっていました。12月に入って穏やかな陽気が続いています。さて、本稿では前回お伝えした上半期の事業結果から、部門ごとの支援計画がどのように進んだのかをお伝えいたします。
************
≪サービス事業別、部門別状況≫
① 支援課 総務厚生担当
事務センターや所内の各部署等と連携をとりながら、給付費の請求業務やプログラムの企画と調整、青葉通信の発行、勤怠管理、実習や見学者の受け入れ、入退所の手続き等の多岐にわたる業務を円滑に遂行するとともに、新規利用者の受け入れを積極的に行いました。
② 支援課 新規事業準備担当(放課後等デイサービス)
東京都や東村山市と相談を重ね、就学時から始める、働くことを目指した早期職業準備トレーニングを特徴とした放課後等デイサービスの事業開始に道筋をつけました。市内の放課後等デイサービス事業所や計画相談事業所、支援センター、特別支援学校の協力もあり、利用希望者の確保もできつつあります。
③ 営業課 営業担当
本年度より営業員を1名増員し3名体制とました。売上高は前年度実績、本年度計画ともに下回りました。加工高は前年度実績を下回りましたが、本年度計画を上回ることができました。
主力のメールサービス関連受注において、計画に入れていたが受注できなかったものがいくつか発生しました。その売上高の不足分を既存顧客の深耕や新規顧客の開拓で埋める営業努力がさらに必要となりました。また、障害者優先調達推進法を念頭にしたと思われる商談の中から、いくつかの案件を受注に結びつけることができました。
メールサービス以外の事業(簡易作業、防災、物販、清掃、データ入力、新規事業)についても充実させていくことが求められているところです。清掃作業については、八潮配送センター、近隣の小児クリニックの室内清掃業務の他に、草取りや絨毯の染み抜き等を受託できました。入力業務については、大規模小売店舗チェーンの顧客データ入力を引き続き受注し、多くの利用者が対応できるようになってきました。
④ 営業課 情報処理係(就労継続支援B型事業、A班)
宛名印刷機2台の買い換えを行いました。また同時に導入したデータベースソフトにより印字出力能力を向上させることができました。
大規模小売店舗チェーンの入力では、受注量は前年に比べて128%と増加しましたが、他の作業との兼ね合いで、法人内他事業所に作業を依存することが多く、当部門での作業量は66%に減少しました。
在宅での就労継続支援B型事業のサービス提供は、自宅の作業環境の整備や訪問による支援の体制を確立しました。現在の利用者は1名ですが、新たな希望者も1名出ています。今後自宅や学校で、在宅作業を念頭においた実習を計画します。
利用者専用の作業マニュアルを作成し、出力作業にも一部携わることができるようにしました。今後、作業経験を積むことができるよう支援を行います。
利用者の多様な障害や変化する状況に的確に対応できるよう、精神障害者、発達障害者支援に関する研修に従業員を参加させました。また、地域の精神保健福祉関係者との学習、情報提供、意見交換を深めるため、東村山市精神保健福祉ケア検討会に参加しました。
⑤ 事業課 就労移行支援係(就労移行支援事業)
前年度までは就労継続支援B型事業の3つの係で課を構成してきましたが、本年度からは就労移行支援事業を含めた4つの係の体制として取り組みました。
在籍利用者数に合わせ、専任の就労支援担当者は1名の体制としました。個別支援計画の作成には可能な限り家族等の参加を促し、利用者も含め情報交換を行いながら個別面談を通じて目標を作成しました。支援計画は実績や達成状況を踏まえ、3ヶ月ごとの見直しを行いました。
就職活動は、ハローワークや各地域の就労支援センターなど外部の支援機関や事業所間と連携して行いました。事業所内においても作業訓練を担当する部署等と連携を取り、より良い支援を行うよう心がけました。こうした取り組みの結果、2名が就職に結びつきました。アフターフォローも職場訪問やジョブコーチ支援を取り入れる等順調に行っています。
就労アセスメント利用者5名を受け入れました。就職者の輩出に伴う利用者数の減少を抑えるため、引き続き支援機関等へ利用者募集活動を行う予定です。
⑥ 事業課 就労継続支援B型事業(3つの係共通の課題と取組状況)
作業にあたっては、仕様書の確認や入荷数量のチェック等の基本作業を徹底するとともに、品質管理を最優先課題として取り組みましたが、数件の作業ミスがありました。原因を究明したうえで、再度基本作業の徹底を図りました。
利用者も含めた全作業者を対象にプライバシーポリシーについての研修を行い、プライバシーマークを取得している意識をさらに高め、個人情報等の漏洩防止に努めました。
利用者の作業量の確保は引き続いて最大の課題です。照合の必要な作業等複雑な工程を含む作業が増えてきていますが、利用者が関わることのできる工程の切り出しを可能な限り行いました。
障害の重度化や加齢に伴う作業能力の低下等によって、これまではできていた作業に取り組むことが難しくなっている利用者については、適性や状況を考慮したうえで随時新たな作業に振り替えました。通所の不安定な利用者が多い部署においては、納期遅れが発生しやすい傾向にあることから、係間で進捗状況を確認しながら調整を行いました。
ヤマト運輸のメール便配達は、利用者が協力し合って業務に取り組んだ結果、個々のレベルアップにつながりました。今後は、年間の課題である配達範囲の拡大を検討します。
八潮配送センター及び館内清掃については、利用者のリーダーが中心になって作業を進めた結果、具体的な指示がなくても作業に取り組める利用者が出始めています。
物販事業については、被災地商品のほかに飲み込んでも安全で安心な口腔ケア商品「オーラルピース」を加え、販路の開拓に努めました。
プログラム活動は、利用者とその家族の意見や要望を取り入れながら常時見直しを行い、内容の充実を図りました。
落ち着いて長時間の作業活動に取り組むことが困難な利用者について、弾力的に休憩を取り入れる等の支援を行い、常時見守りが必要な利用者については担当係やフロアを超えた支援を行いました。
⑦ 事業課 一係 (就労継続支援B型事業、B班、C班)
ミスが起こらないようチェック体制に十分注意を払い作業を行いました。可能な限り外注費を抑えるように調整して作業にあたりました。通所が不安定な利用者については、家族や関係機関と相談しながら支援を行いました。一般就労を希望する利用者への支援については、本人の意欲を高められず、思うような支援には至らなかったことから、下半期の課題とします。
⑧ 事業課 二係 (就労継続支援B型事業、D班、E班)
ミス、ロスを抑えるため、仕様書の確認を随時行い係内で情報の共有を密に図りました。メール便配達については複数の従業員で支援できる体制としました。体調の不安定な利用者については、家族や医療機関と相談し必要に応じ所属変更等を行いました。一般就労を希望する利用者に対し、関係機関と連携し情報を共有しました。現状の日中支援だけでは支援が行き届かない場合は、家族に働きかけ嘱託医に繋げました。障害の特性に配慮し、必要に応じて席替えを行いました。
⑨ 事業課 三係 (就労継続支援B型事業、F班、G班)
病院や支援センター等と連携し、安定した通所ができるよう支援しました。生活面の安定に繋がるよう、社会資源の紹介や情報提供を行いました。現状の日中支援だけでは支援が行き届かない場合は、嘱託医に相談し医療へ繋げることができました。引き続き、SST(ソーシャルスキルズトレーニング)を行える体制を検討中です。清掃リーダーの指導により、清掃に携わることのできる利用者が増えました。
************
12月5日の土曜日は、午前中を特別セミナーとして学芸大の菅野敦先生にダウン症候群の成人期支援について、ご講演をいただきました。当センターの従業員ばかりでなく、利用者、ご家族の皆様、他事業所の従業員等にも多数ご参加いただき、このテーマについての関心の高さがうかがえました。2時間30分あまりのお話でしたが、参加者からは、もっと時間があれば、の声が聞かれました。午後は忘年会で、利用者の皆さんとカラオケで盛り上がりました。
12月26日の土曜日は通常の通所日です。お客様からお預かりしている仕事を追い込む日になりそうです。今年もあとわずかになりました。体調に気を付け年末年始を楽しみに頑張りましょう。