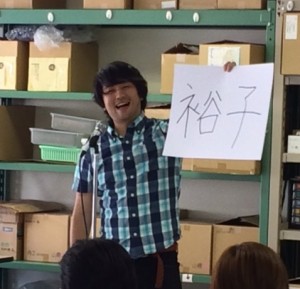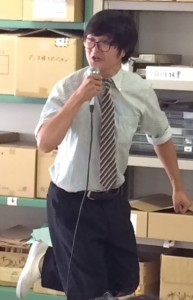2015.9.15
青葉通信9月号巻頭言
事業所長 武者明彦

蝉の声がいつの間にか秋の虫の声にかわり、だいぶ日も短くなってきました。夏と秋とが日本上空でせめぎ合っているようで、このところすっきりと晴れ渡る日がほとんどありません。さて当センターでは本年度の事業計画で、下半期を目途に放課後デイサービス事業を実施する準備を進めることにしていましたが、ようやくその概要がまとまってきましたので、お知らせします。
*********
■放課後等デイサービス事業について
この事業は、障害のある(療育が必要と認められる)子どもたちの学齢期における支援の充実のため創設されたもので、障害のある子どもに対し、放課後や長期休暇中に療育の場(日常生活動作の指導、集団生活への適応訓練等)を提供する事業であり、放課後等の居場所、また、レスパイトケア(ご家族に代わり一時的にケアを代替することで、日々の疲れ等をリフレッシュしてもらう家族支援サービス)としての役割を担う事につながる事業です。障害児のための学童保育と考えると理解しやすいでしょう。
■トーコロあおば就労サポートセンター「アリーバ」
当センターが実施する放課後等デイサービス事業の名称は、トーコロあおば就労サポートセンター、愛称は「アリーバ」です。アリーバ(arriva)はスペイン語の副詞で「上へ」という意味です。頑張る人を応援する気持ちを表す意味があり、サッカーの応援などでサポーターが選手を応援するときに掛ける声援です。もちろん巻き舌でアリーバ!
アリーバは、学校卒業後の就労に向けた早期職業準備訓練に特化したサービスの提供を最大の特徴としており、一人ひとりの個性と発達状況を把握して、無理のない支援計画を作り、ご家庭や学校と連携した支援を目指します。
■アリーバのサービス内容
①主な対象者:特別支援学校などに通う、中~高等部程度の障害がある児童で、卒業後に一般及び就労支援施設での福祉的就労を希望している方。
②対象区域:東村山市と送迎可能な近隣市(清瀬市、東久留米市、所沢市)。
③利用定員:一日当たり10名。
④利用時間:原則、月曜日から金曜日の午後2時~6時、学校の長期休校日は午前11時~午後6時(年間スケジュールによります)。
⑤平成27年11月1日を開所日の目標とします。詳細は確定次第お知らせします。
■アリーバの活動内容
①社会で必要になる基本を育てます(社会人として大事なことを身につけます)
あいさつができる・身だしなみに気を配る・整理整頓ができる・手洗いなを習慣づける・タイムカードを打刻する・時間を守る・予定や指示を確認する・協調性を養う・ルールや規則を学ぶ・地域交流の機会を提供など。
②生活面の自立度を向上させます(自分でできる事を増やします)
公共交通機関を利用して通勤(通学)の練習をする・交通規則を学ぶ・自分の気持ちを表現できるようにする・生活力を育てる(清掃、雑巾絞り、テーブル拭き、ごみの分別、昼食などの買い物体験、配膳、食器洗い、洗濯、衣類たたみ、図書館やスポーツセンターなど地域資源の活用)など。
③体験を通じて働くことの理解を広げます(働くことってどんなことかを体験します)
作業を体験する(作業手順や指示を守る、正確な作業を行う、活動や成果の責任意識を育てる、作業時間の意識を育てる、報告・連絡・確認・相談の習慣化、姿勢の保持など)・体験を通じ作業適性や障害特性を把握する・仲間と共に働く意識を育てる・
職能訓練、職場見学、職業体験の機会を提供する・ハローワーク見学など。
④就労生活に役立つ各種のプログラムに参加できます
パソコン・スポーツ、ウォーキング・昼食の買い出し、調理・図書館での読書・散歩など。
⑤個別に相談できます(卒業後の進路や心配事について何でも相談できます)
ご家族への相談援助・学校、児童支援関係機関との連携・ご家族や学校への進路相談援助・企業見学などの機会提供・活用できる制度やサービスの説明など。
■アリーバの利用にあたって
他のサービスと同様に、自治体から支給決定を受ける必要がありますが、利用に際して療育手帳や身体障害者手帳は必須ではないため、学習障害等の児童も利用しやすい利点があります。月額の利用料は原則として1割が自己負担で、所得により上限があります。
*********
秋の味覚が店頭に並び始め、食欲が目を覚ましてきたようです。夏の疲れも出るころなので、よく睡眠をとって風邪など引かないように気をつけたいものです。