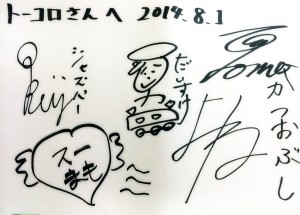2014.11.15
青葉通信11月号巻頭言
事業所長 武者明彦
11月に入り朝晩冷えこむ日が多くなってきました。街にも紅葉が下りてきて目を楽しませてくれています。本稿では、日本障害フォーラム(JDF)みやぎ支援センターの要請でゼンコロが行った被災地調査に私も参加してきましたので、現地の実情などをレポートします。
***********
JDFでは、東日本大震災直後から岩手、宮城、福島の三県に支援センターを開設して、障害者の生活支援や調査活動を続けてきましたが、宮城県内の島嶼部の仮設住宅で暮らす障害者の生活状況が未調査であったため、構成団体である一般社団法人ゼンコロに調査依頼がありました。この要請に応えて山形コロニー、長野コロニー、東京コロニー(コロニー東村山、コロニー中野、トーコロ青葉ワークセンター)から総勢7名が、3つのチームに分かれて地域を分担して調査を行いました。私のチームは今年10月3日から10月7日までの間、塩竈市浦戸諸島 (野々島、桂島、寒風沢島)と、東松島市宮戸島 (宮戸小グラウンド、月浜地区、室浜地区)の仮設住宅を訪問してきました。
結論から言うと、我々が調査した6か所の仮設住宅には、現在調査対象となる障害者はいなかった、と言う事になります。しかし視点を変えれば、島々には多くの高齢者が歩行困難などの障害を抱えながら、急峻な島の高台にある仮設住宅で暮らしています。仮設で暮らす住民の方や自治会長、(地)区長の皆さんからうかがうことができた島の暮らしをお伝えします。
① どのようにして助かったのか(複数の住民の話、島民全般の状況)
野々島:地震の直後に塩竈市職員の津波が来るとの呼びかけで高台の学校に避難した。津波による死亡者はなかった。カキの作業中に地震があり身一つで避難した。地震と同時に家から裸足で逃げた。島の反対側からも波が越えてきた。竹やぶから塩水が噴出した。
桂島:地震が来た時に高台にある学校に避難した。津波による死亡者はなかった。現在仮設内に障害者はいないが、仮設外に家族同居の引きこもりの方がいて、行政も状況を把握している。高台にあるペンションの主人は地震直前に塩竃市内にいたが急遽島に戻って無事であった。ペンションやクルーザーは無事だったが、塩竃市においてきた車は全壊した。食材や洋服、寝具を被災者に提供した。
寒風沢島:地震が来た時に小学校跡地に避難した。その後家に引き返した3人が津波で亡くなった。位牌だけを持ってお寺に避難し助かった。カキや海苔の養殖で生計を立ててきたが港がほぼ壊滅し、今年1軒のみ事業を再開できた。
宮戸島:震災で島内では40歳代の引きこもりの男性1名が死亡、懐中電灯を握りしめていた。現在島に障害者はいない。被災した民宿は観光客相手に地引網などを再開した。
② 仮設住宅の生活で困っていること(複数の住民の話、島民全般の状況)
野々島の状況:仮設住宅は夏暑く冬寒い、石油ストーブが使用できないので暖まらない。医療は診療所に週1で医師が来る。買い物は生協の車での販売が週1回ある。生鮮品などは塩釜で買い、ヤマト宅急便で送ってもらうので困っていない。年内に復興住宅ができて全員が移れる予定。
桂島の状況:塩釜市、区長、民生委員などが連携して対応しており問題はない。復興住宅の基礎までできており年内に全員が移れる予定。復興住宅の工事に伴い騒音、ほこり、景観の悪化があったので申入れして配慮してもらった。地域では漁船など無くした人と残った人の軋轢がある。医療は診療所に週1~2日医師が来る。買い物は生協の販売が週1回、民間業者の販売が週1回ある。生鮮品などは塩釜で買い、ヤマト宅急便で送ってもらう。たくさんボランティアが来てありがたかった。
ボランティアが持ち込んだテントが貯蔵庫として使われていた。取材中に獲れたてのハマチが差し入れられて、島民同士の助け合いが基本にあることがうかがわれた。
寒風沢島の状況:障害者が1名いたが震災後島外へ移って現在島に障害者はいない。住民の話、被災住宅から金品がなくなることがあり大変な思いをした。島外で働きたいという息子に思いとどまってもらいカキの養殖を続けている。年内に復興住宅ができて全員が移れる。
塩竃市の3島のひとり一人の状況が共有されている様子。島のコミュニティーの強さがうかがえた。
宮戸島の状況:島内3か所の仮設住宅に島外の矢本地区や野蒜(のびる)地区の住人も避難している。県の方針で防潮堤などの嵩上げが優先し、事業復興が後回しになっている。仮設住宅から家を確保できた人からそれぞれの地域に帰ってゆくので毎日のように住人が居なくなりさびしくなる。復興住宅ができると皆移れる。復興住宅には障害者の夫婦が入居する予定。
③ 調査活動で感じたこと
今回の調査対象の仮設住宅には障害者はいないことが確認されました。しかし、仮設の住民のほとんどが高齢者と思われ、歩行困難な方も多く見られました。何れの島でも復興住宅の建設が急ピッチで進んでいて、仮設暮らしの不自由さからは年内(だいぶ遅れているか?)にも脱却できるようですが、島嶼部でも小中学校の統廃合が進み、子供もその親の世代も島を出てしまい、高齢者だけが住む孤立した島になりかねない危険性を感じました。島の暮らしを支えてきた強力なコミュニティーが維持できなくなるのかもしれません。
また、防潮堤や住宅地の嵩上げが優先されていて、どこを見ても重機が入り土の山が築かれていますが、一方島を支えていたカキや海苔の養殖、漁業、観光などの仕事がほとんど壊滅している事への対策が後回しになっていると感じている住人もいます。嵩上げが終わった土地には誰も住んでいないと言う事にならないよう、安全対策と並行して、産業振興や景観維持に力を入れる必要があることを痛感しました。
仮設暮らしに不自由を感じている人は案外少ない様子でした。医療機関は週1回、商品の販売も週1回などの状況ですが、島の暮らしはもともと都市部に比べれば不自由を伴っており、これは震災以前から変わっていないものと思われるので、特別不自由と感じていないのかもしれません。
***********
寒風沢島では、仲間同士で資金を出し合い、自力でカキの養殖事業を復興させた皆さんが、今年完成したばかりの作業場でカキ剥き作業をしていました。今シーズンの解禁日と言う事で、剥きあげたばかりのカキを分けていただき食することができました。言うまでもなく寒風沢のカキの味は格別でした。ネット販売も始めたとのことですので、この機会にお取り寄せをしてみてはいかがですか。島の特産品を味わう事が、新しい復興支援につながるかもしれませんね。